インタビュー「人類の進化200万年をさかのぼり、心の発達を科学する」 (2/3)

マネをすることで仲間意識が生まれる
こども研 最近の若者の間で盆踊りが復活してきているという話も聞きますが、それもオキシトシンの放出と関わっている、近代社会への反動的な現象なのかもしれませんね。
明和教授 「カメレオン効果」と呼ばれる現象があります。ヒトは誰かから真似される、同じ動作を共有すると、その相手のことを信頼したり、親和的な感情を抱くのです。ダンスも同じです。一緒に踊っていると仲間意識が生まれる。
こども研 同じ動作をすると,なぜ親近感が生まれるのでしょうか?
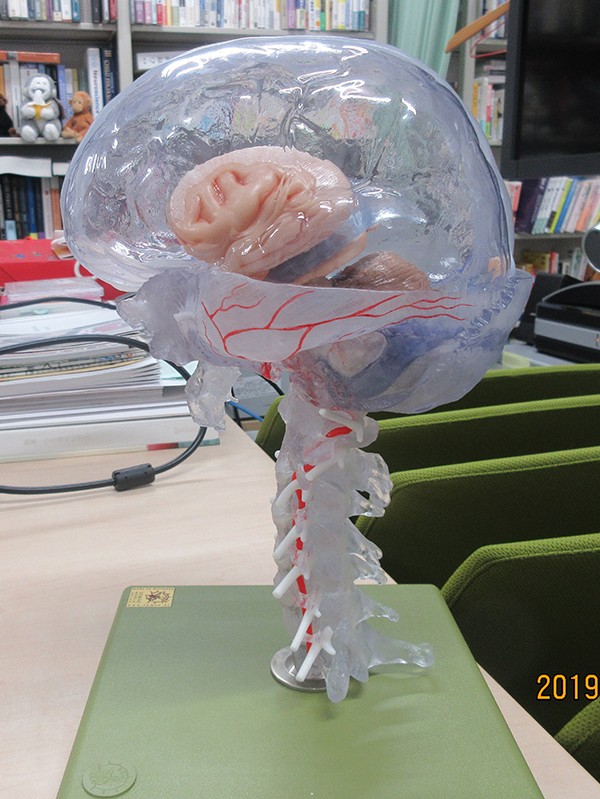
こども研 そうすると社会学の分野で言われている「グローバリゼーションによる個の断片化」で、共通体験が失われていくことの影響は大きいですよね。共通の体験があったとしてもネットでのヴァーチャル体験が中心になっていくとすると、そこでは身体を他者と共有する経験がはく奪されるから、オキシトシンが出にくくなっていくのかもしれないですね。
明和教授 その科学的検証はこれからです。ここで指摘しておきたいのは,私たちの世代は、脳が発達する時期に色々な大人と身体を介して関わるというリアルな体験をして育ってきていることです。私たちの脳は、こうした経験を得てすでに完成している。しかし、これから生まれてくる子どもたちは、ヴァーチャルとリアルが融合するという未曾有の環境の中で育つことになる。誰かと身体接触する、身体経験を共有するという日常は希薄になっていくでしょう。子どもたちの脳は未成熟です。こうした新たな環境は、子どもたちの脳の発達、たとえば,先述のシナプス刈り込みなどにも大きな影響が出てくるはずです。これまでの環境とはまったく異なる情報処理が行われるようになるわけですから。体性感覚野は特に変わってきていると思います。この仮説はあと数十年後には検証されるでしょう。テクノロジーは指数関数的に発達していますから、さらに予測不能な事態が次世代の人間の脳に起こるかもしれません。
こども研 今までの人間の順序でいくと、まず身体性のあるリアルな体験があってからメディアでの体験をしたわけですが、その順序が逆になってしまうと、アタッチメントやぬくもりがあることが嫌になってしまうことがあるのではないでしょうか?
明和教授 他個体と身体経験を共有することでオキシトシンを高め、社会関係を築いていく。こうした生体システムをもった人類は、今後新たな環境に適応できなくなって滅びていく。身体に対する感受性がさほど強くない個体だけが生き延びるということもあり得るかもしれません。ただ、人間の身体とその生体システムは何百万年という時間をかけて獲得されてきたものですから、この20~30年でそう簡単に変わることはないと思います。しかし、環境と生体システムのミスマッチは今後いっそう大きくなっていくはすですから、精神疾患を発症するリスクはどんどん大きくなっていくと思います。
こども研 長い時間をかけてつくられてきた人間の体ですが、その人間の体が適応できないような環境を人間自身がつくってしまったということになりますね。そんな環境変化に対抗しようという揺り戻しが人間自体から起きてくることはあるのでしょうか?
明和教授 まさに、そこのところで私は基礎研究者としての役割を果たしたいのです。生物にとって身体性、環境と身体の相互作用がいかに重要かを理解してもらうために、本を書いたり講演活動を行っています。とくに,脳が未成熟な子どもたちと接しておられる現場の方への啓蒙に力を入れています。スマホを見ながら赤ちゃんに授乳していると、脳の感受性が一番高いときの絶好の機会を逃すことになりますよと。母親と見つめ合いながら身体接触をすることで、人間にとって大事な生体システムができあがっていくのですよ、と。



