インタビュー「無限の可能性ではなく、有限の特性を信じる」 (2/2)

非認知能力を高める方法
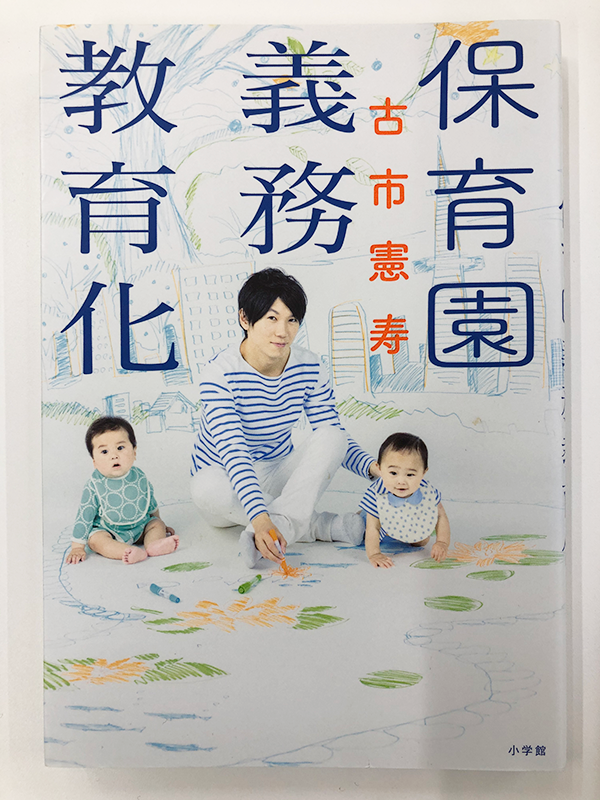
こども研 最近の教育界では、学力以外の非認知能力に注目が集まっていますが、その辺については、どうお考えですか?
古市 『保育園義務教育化』という本でも書きましたが、僕は乳幼児教育を拡充していくことが、非認知能力を効率よく高めていく最良の方策だと考えています。日本では、個人レベルでも国レベルでも、乳幼児教育ではなくて高等教育にお金をかけてますよね。でも、教育経済学の知見によれば、乳幼児段階での教育効果の方がはるかに大きいことが判明しています。
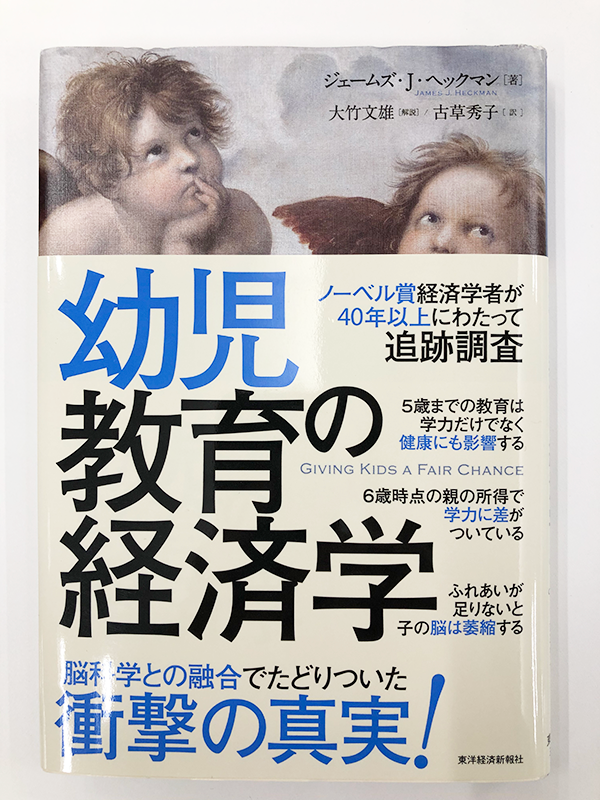
こども研 ご著書でも書かれていたヘックマン教授の調査のことですね。
古市 ただし、非認知能力をまるで教科のように扱うのは違うと思っています。学校教育で学ぶ以前に、乳幼児の段階で多くが体得されてしまうわけですから。それに乳幼児の段階であっても、生まれつきの個性や資質という遺伝的要素も無視はできないですよね。
古市 教育はむしろ、個人の無限の可能性を信じるものではなくて、個人の好きなこと、得意なことという特性を伸ばしてあげる方が大事なのかなと思います。逆に今は、誰もが無限の可能性があって、いつからでも勉強できて、と考えられすぎていて、それが子どもにとって辛いシステムになっているのではないでしょうか。
こども研 全員が特定の理想形を目指す必要はないですよね。
古市 子どもの数が減っているので、親としても一人の子どもに色々なことを学ばせたいという気持ちは分かるのですが、いろんな可能性があるはずだと期待すぎじゃないでしょうか。
こども研 なるほど。
古市 それよりも「主体性」ということが大事なのではないかと思います。たとえば、以前ノルウェーの保育園を取材して面白いと思ったことがあります。子どもが保育園に着くと、先生はまず「今日は何がしたい?」と聞いて、子どもがしたいことを中心に1日を過ごしているのです。これも、先生の数が多いからできることではあって、日本の保育園の場合は先生の数が少ないので、「みんなでお遊戯をしましょう」とか、どうしても集団行動になってしまいますよね。そうすると指示待ちの子が多くなってしまって、自分から「こうしたい」という志向に慣れることなく成長してしまうことになります。昭和だったら、主体性がなくても兵士のように言われたことを聞く人材が重宝されましたが、今は違いますよね。
こども研 これからは、ますます何が正解か分からない時代になっていくと思いますが、少なくとも「自分はこれをやっていたら楽しいな」とか、「夢中になれる」というものがないと辛いですよね。大人としては、それを発見してあげるのが一番なのだろうな、と思います。
古市 そうですよね。たとえば高校や中学でも、大学みたいに生徒の希望に合わせた選択式の授業をもっと増やしてもいいと思います。自分でやりたいことがはっきりしていると、そこから逆算して「じゃあ、英語を勉強しておこう」とか「この科目も必要かな」という風になる。認知科学では内発的動機つけといいますが、動機づけが外部からの押し付けだと人はなかなか本気になれないでしょう。自分から気づいて、これをやらなければと思うと、急にやる気が出てくるものなんですよね。
注:ジェームス・ヘックマン米シカゴ大学教授(2000年ノーベル経済学賞受賞)が行った幼児教育の費用対効果に関する定量調査



