インタビュー「次の時代に求められる、ことばの力」 (1/2)
子どもの読解能力が低下していることが近年大きな問題になりつつあります。 改めて今、言葉を扱う能力をどのように養っていくべきなのかが問われているのではないでしょうか。 今回は、教育界のキーマンである上智大学・奈須正裕教授に、「ことばの力」をテーマにお話しを伺いました。

「書く」ことが苦手な日本人
八木 今回は当研究所の諮問委員も務めていただいている、教育界のキーマン、上智大学の奈須教授にお話を伺います。当研究所は「こども」「ことば」「教育」に関連する調査研究を行っておりますが、先生は次の時代に求められる「ことば」の力、「ことば」の教育についてどのようにお考えですか?
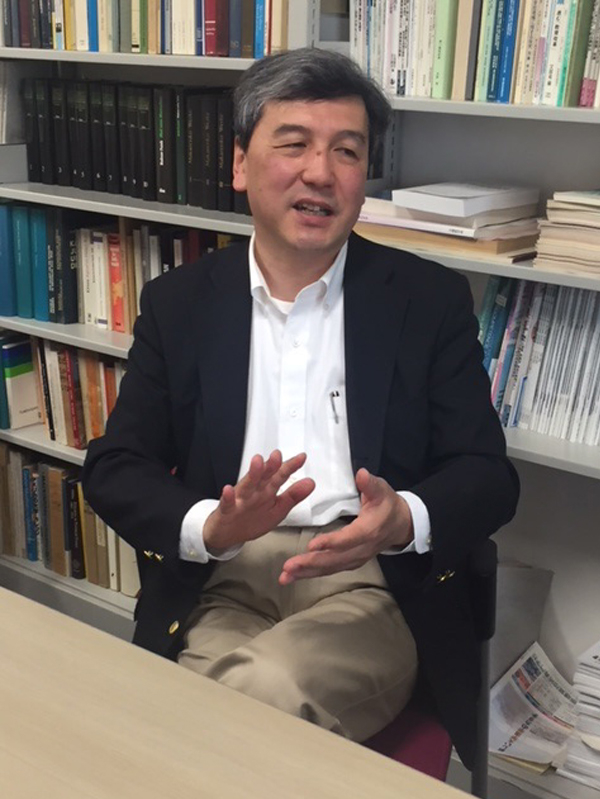
多くの人にとっての「母語の教育」、いわゆる「国語」の教育をやるときには、母語を学習言語のレベルまで引き上げていくことが必要となります。学習言語というのは、その言語を思考の道具にするとか、それを思想の表現のツールにするというレベルでの言語のことをいいます。このレベルでの言語は、いろいろな教科を勉強する時の道具にもなりますし、抽象的・論理的に考えられる、とか、それを的確に表現できるとか、すべての学びの基礎になります。その中でも、「読む」ことに比べて「書く」ことは当然難しい。だから、ある意味では文章を生成する、「作文」する、というのが、言語教育の中心にあるべきだと思います。なお、「話す」ことばである「音声言語」も大事ですが、「書く」ことばである「文字言語」の方がよりフォーマルで、学習言語としてきちんと教えなければなりません。日本のこどもが海外に行った時に、ことばをすぐに覚える、というのは、音声言語です。日常会話まではカバーできるが、いわゆる学習言語といわれるレベルまではカバーしにくい、という特徴があります。
それでは、日本語の文章生成、「書く」こと、いわゆる「作文」ですが、この分野には、どのような課題があるのでしょうか。日本の学生が海外に行った時に、日本の学生は論理性がない、論理的でない、とよく言われます。しかし、彼らの思考が論理的でないのかといえば実はそうではなくて、論理的に考えたことを表現する技法とか型を教わっていない、ということなのです。試しにある種の型、論理的に表現し、説得的に伝える型を教えた上で留学させると、絶対にそんなことは言われません。日本の学生は、小・中・高校でそういう練習をしていない、ただそれだけなんです。では、小学校、中学校が何をやっているかというと、「読書感想文」と「行事の作文」ですね。場合によっては、それが「作文」だと大人も思い込んでいる。ヨーロッパでもアメリカでも、そんなことはやっていません。
日本語教育の歴史は明治時代に日本の教育が始まった時までさかのぼります。当時「作文」は、完全に大人の文章を真似て、全くこどもに体験、経験のないことを書かせるものでした。明治時代は、それがとても多くて、絵も、いわゆる図工の領域も「臨画」といって模写でした。お手本を正確に模写する、それが明治期の教育。完全な暗記で、意味は重要ではなかったんです。それはさすがによくない、とわかったのは大正時代。第一次大戦後、いわゆる大正デモクラシーの時代に、日本は大正自由教育といって、こどもの心や発達段階を全く無視して、大人が教え込むことは、とても良くないと議論された時代だった。
作文の場合、「赤い鳥」という児童文学雑誌を中心に、いわゆる児童文学運動が起き、中心人物だった作家の鈴木三重吉は、こどもにとって、まったく経験も実感もない文書をただ模写させるというのはことばの教育としてはとてもおかしい、と課題提起しました。つまり、こどもはいろいろなことを考え、感じているから、こどもがリアルに経験したことを綴って、と同時にそれに対していろいろ考えていることや思いを書く、ということを中心にすべきであると訴えました。こどもに自由に書かせなさい、そこで発露するこどもらしい感情が大事だ、ということです。明治時代、徹底して型を教えていたのに対して、「型を教えない」「型が悪だ」という考え方です。民主主義が大事にされたこの時代に、こどもたちが共通して経験している感動や思いがあるのは行事です。運動会とか遠足とか、皆が経験している楽しい行事を足場に、みんなで書く。ただ、運動会や遠足の何をどんな風に書くのは自由でよいと。かけっこを書く子もいれば、お弁当を書く子もいていい。面白いのは、それを皆で並べてみた場合に、一つ共通の経験に対して個性的で多様な感じ方があり、表し方がある、ということじゃないか、となったわけです。それ自体は悪いことではありません。アメリカでも実は1930年代~40年代には、そういう考え方が出てきていて、世界的な潮流でした。
ちなみに、日本語の「読み」、いわゆる「読解力」ついては、1930-40年代に、科学技術立国をめざした中で、情緒豊かで楽しい物語を読ませると同時に、科学的で論理的な文章を読ませることもしました。だから、実は読解についてはよくできるんです。最大の問題は、読解でやっている構造的で論理的な文章を、「書く」機会は一切なく、読むことと書くことがシンメトリーになっていないということなんですね。
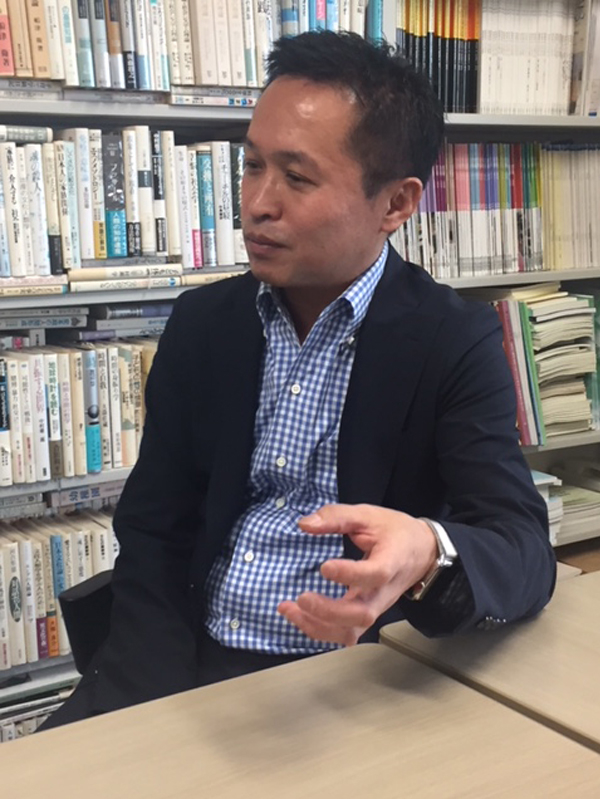
奈須 例えばアメリカの場合、ギリシャ・ローマ以来の修辞学(※1)に基づく型を教えていました。要は、伝統的な西洋における弁論・叙述の型ですね。特に、ベトナム戦争以降、アメリカでは高等教育が爆発的に拡大し大学進学率が一気に上がったのですが、その時に、論理的に考えられない、表現できないこどもたちが高等教育を希望してきて、それが非常に困るということになり、これがひとつの契機になって、1970年代~80年代にかけて初等中等教育でも、論理的に考えて表現するための作文教育をちゃんとやろう、という話になっていきます。その際、小学校でも、最初にまず結論を言って、そのあとに3つ位の根拠となる事例を示し、それを総括して、最初の結論をもっと強く説得力を持って語る―ファイブパラグラフという手法を教えるようになりました。最初のセンテンスがあって、それに対して3つの事例を出し、最後に結論(コンクルージョン)。これを小学校3年生くらいから教えています。各州の評価規準があって、小学校の学力として身につけるものとして、学習目標と規準が明確に設定され、指導を要請されています。
学習の達成度を明らかにすることを求められるのは、「エッセイライティング」です。学術研究とかビジネス、日常生活に対する有用性から考えられた技法で、論理的である、説得的であるということを大切にしながら、個人の解釈をちゃんと入れなければならない。事実をただ並べるだけでなく、その事実を自分はどう解釈して、何を強調してこの論理を形成するか、ということを徹底します。
もう一つの柱として、欧米にはエッセイライティングにならぶ「クリエイティブライティング」というのがあって、空想のオリジナルな物語を創作します。エッセイライティングという論理的な説明文と、クリエイティブライティングという物語づくりという二本立て。一方で、日本ではクリエイティブライティングは一切やらないですね。
なお、アメリカでは、「読解」については、原則多読です。たくさん読んでいるうちに自然に読めるようにする、というやり方です。たくさん読み、たくさん書くことの両輪で、論理の構造を理解する、そういう考え方に立っています。



